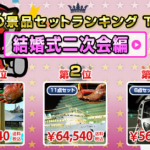風呂という文化は世界各国にあるもののお湯に浸かるという沐浴が庶民レベルで日常習慣になっていた地域というと、ローマ・ギリシャ文明地域と随分離れた日本ぐらいであります。
古代ローマには今でいう銭湯となるテルマエが街の各所にあったということは有名ですが、ローマ帝国の衰退とともにヨーロッパでの入浴文化は変化していき、シャワーというかけ湯に変化していったのはご存じだと思います。
一方アジアなどでも中国や朝鮮半島において湯船につかる入浴の習慣はあったものの、貴人に限定されたもので湯殿でのんびりするといった行為は庶民には縁がないモノでありました。
ただこうした宮廷文化も徐々に簡素化されていき湯船はあくまでも湯を溜めるだけのモノとなり、王族にいたるまで入浴かけ湯で済ませ湯船に浸かる入浴方法からは徐々に遠ざかっていく傾向がありました。
これらの入浴習慣はアジアの西洋化が終わる時期までかわることがなく、古来から同じ方法でお湯を溜めた湯船に浸かるという方法で入浴する文化は海が隔離した日本にのみ残ることとなります。
では日本の温泉においてもっとも古く登場する温泉は何処になるのでしょうか?
これは夏目漱石の小説「坊ちゃん」にも登場する、現在の愛媛県松山市に位置する道後温泉と言われております。
その歴史は他の温泉とくらべても群を抜いて古く、弥生時代の土器などが出土することから3000年ほど前から利用されていたものと考えられるほか、万葉集などの記録にもこの地についての記載があり、人類学的にも文献的にも最古の温泉と呼ばれております。
この道後温泉、有馬温泉、白浜温泉の3つを指して日本三古湯と呼びます。
ただこれとも異なるモノとして山形県の蔵王温泉などは日本武尊の伝承の中に登場しており、神話伝承という不確定さはあるものの、当時が西暦110年前後と考えると弥生時代の道後温泉には敵わないものの文献として認知された中では蔵王温泉も最古の温泉になるかもしれません。
こうした文字伝承や口頭伝承の文化というのは日本においても貴人を中心としたものであり、かなり後天的なモノになります。
ひょっとすると猿が自然に温泉に浸かるように、集権文化がなかった時代からすでに日本人は温泉に浸かるということを普通に行っていた可能性すらあるのです。
最終更新日 2025年6月15日 by kitairu