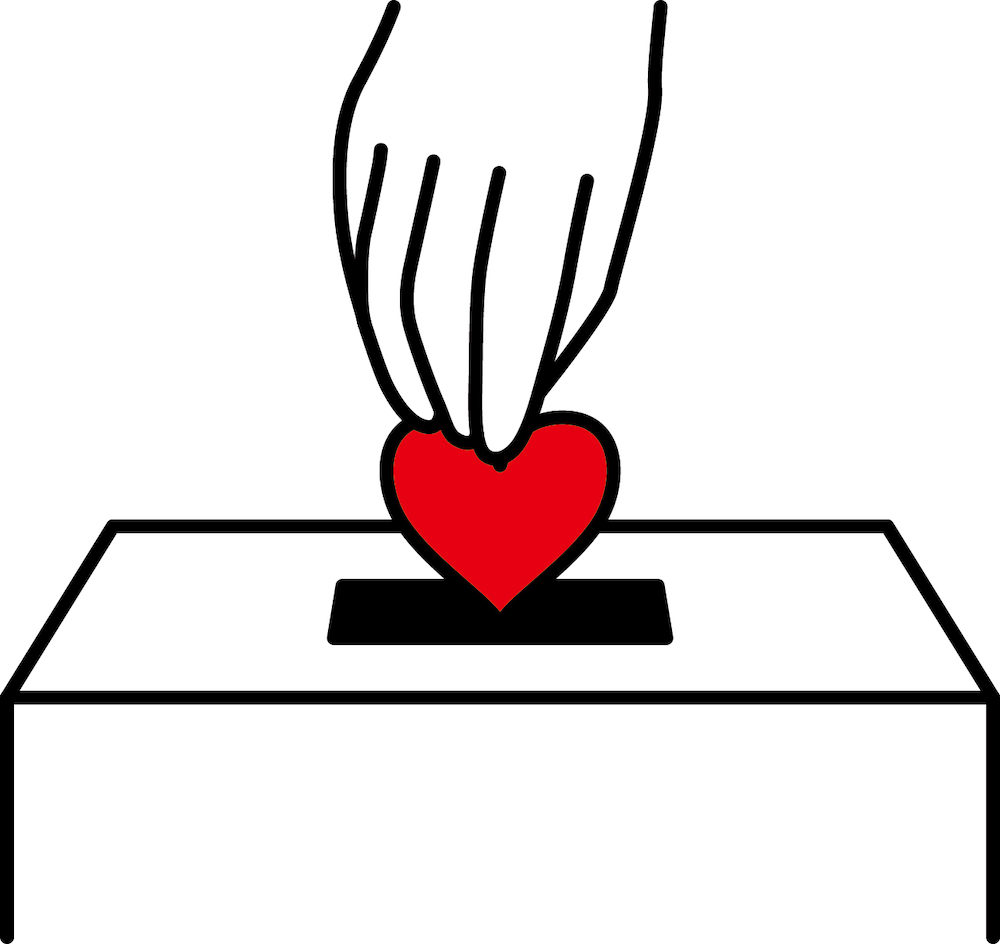正式名称を国際連合児童基金(United Nations International Children’s Emergency Fund)、英語の頭文字をとってユニセフ(UNICEF)と呼ばれています。
1946年第二次世界大戦で被災した子供たちを支援するため、緊急で設立された国際機関です。
1965年にはノーベル平和賞を受賞しました。
民間からの募金を推進するため、先進国を中心に34の国と地域に設置された各国ユニセフ協会と協力協定を結んでいます。
1955年に日本ユニセフ協会が設立
1949年から1960年までは日本も主要な被援助国として、ユニセフから支援を受ける国の一つでしたが、1955年には「日本ユニセフ協会」が設立されました。
その後、日本の国際連合加盟の承認を経て「日本ユニセフ委員会」と正式に承認され支援する立場となります。
日本は世界を支援する上で欠かせない国となっています。
あくまで民間からの支援を担当し、政府からの支援はUNISEF本部が担当します。
最初は物資中心の支援であったものの、生活の自立がなければ援助し続けても変わらないと気づき方針を変えました。
親に対する栄養の啓発活動など、援助内容に変化が見えるようになります。
目的は世界中にいる全ての子供の命と権利を守るための活動を行うことです。
世界190か国以上の国と地域で支援
最も支援が届きにくい国の子供たちを最優先に、世界190か国以上の国と地域で支援を続けています。
活動分野や多岐にわたり、どの分野も子供たちが安全に成長し権利を得るためには必要な支援です。
世界には5歳になるまでに命を落とす子供が、年間540万人もいるといわれています。
そのような状況をなくすため、乳幼児期から適切なケアを受けられるようにします。
予防接種の普及・安全な水や衛生環境の確保・母乳育児の推進・栄養改善などを保健分野から、子供たちが早く命を落とすことなく健やかに育つようサポートします。
世界中でHIV/エイズの治療や感染予防に関する研究が行われ、2004年のピーク時より減少したものの、まだまだこの病に苦しむ人がいるのが現状です。
2030年までにエイズをなくすという目標が国際的に掲げられていますが、感染予防や治療の提供などの取り組みが遅れています。
エイズのない世代を実現するため、HIV/エイズ分野でも地道な活動に取り組んでいます。
水と衛生問題
子供たちが安全に生活する上で欠かせないのは、水と衛生問題です。
劣悪な環境では病の回復も遅く、水質が悪ければ命を落とすきっかけにもなります。
感染症を引き起こしたり、下痢をして亡くなることがないよう、給水設備の設置や衛生的な環境を実現するためトイレの設置 などを行います。学校や保健所などで衛生習慣を定着させるため、手洗いに石鹸を使うよう指導もします。
安全な水と衛生的な環境を確保できるよう活動しています。
幼い子供たちの栄養不良は深刻です。
毎年数百万という子供たちが重度の急性栄養不良により命を落とす現実があります。
子供たちの栄養状態を改善するため、必要な物資を届けるだけでなく治療と栄養指導を行います。
教育を受ける権利が得られるよう支援
教育を受けることができない子供たちのため、学校の建設や教育資材の提供、先生の育成を行って、多くの子供たちが教育を受けられるよう支援します。
勉強だけではなく安全にスポーツができる場所を提供し、心のケアが必要な子供たちにカウンセラーの派遣もします。
基本的人権である教育を受ける権利が得られるよう支援を行います。
子供には環境や教育だけでなく、命の危険にさらされている場合もあります。
児童労働・自動結婚・人身売買など戦争に使われることもあります。
抵抗する術を持たない子供たちを保護することも大切な活動です。
民族やジェンダー障がいなどから起こる差別をなくす活動も行います。
差別に関する問題は根深く、一朝一夕で解決できる問題ではありません。
誰もが受け入られる社会の実現を目指し、様々な場面で啓発と活動を行っています。
まとめ
女性的であること、男性的であることの概念は社会的・文化的に構築されたものです。
この概念に縛られた結果、女性の社会進出が遅れ活躍が阻害される原因ともなっています。
国によっては女性が教育を受けられないこともあります。
ジェンダーの平等を推し進めることでより良い社会の実現を後押しします。
紛争や災害などで緊急事態となった場合は、速やかに緊急・人道支援を行います。
こうした活動をする上で1989年の国連総会において採択された「子どもの権利条約」を指針としています。
幼い子供たちは大人たちに従うことしかできず、自分たちで身を守り声をあげる術を持ちません。
どれほど劣悪な環境で育ち、ひどい扱いを受けても文句は言えないのが現実です。
彼らの声を代弁し権利を擁護するための団体です。
子供たちの現状を調べ、現実的な政策提言を各国の指導者や国際社会に対して行います。
最終更新日 2025年6月15日 by kitairu